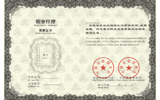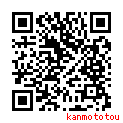乳房のしこり 乳腺症
乳腺症は、成熟期の女性に多くみられ、乳腺の増殖、退行、変性などが複雑に絡み合って起こります。乳がんと同じくエストロゲンという女性ホルモンが関わっていますが、がんとは全く違う病気です。エストロゲンのバランスが乱れることで起こり、主な症状には、片側または両側の乳房の痛み、大小不同のしこりの出現、乳頭から分泌物が出ることもあります。月経前に痛みが強くなったり、しこりが大きくなったり、月経後症状が軽くなることが多いのも特徴です。
また、一部の乳腺症には、液を入れた袋状のしこり(嚢胞)をつくることもあります。これも女性ホルモンの影響でできるといわれ、数や大きさはさまざまですが、表面がつるっとしていて境界のはっきりした半球状のしこりとして触れることができます。
嚢胞は悪さをすることがなく、もちろん乳がんにもなりませんから、特に心配いりません。通常はそのまま経過をみていきます。大きな嚢胞がある場合には、注射針を刺して中の液体を抜きますが、これでしこりが消えてしまうこともあります。
一方の乳がんは、ほとんどが乳管にできます。がんが大きくなると、わきの下にあるリンパ節に転移することがあり、リンパ液や血管を通して体のあちこちに広がります。乳管の組織が細胞分裂するときにDNAが傷つくことで発生し、これに女性ホルモンのエストロゲンが大きく関係してきます。エストロゲンは発がん性物質ではありませんが、乳管の細胞分裂を促す作用があるため、結果的にがん細胞の発生と増殖の手助けをしてしまうのです。
現代の日本女性は、食生活の変化によって初経が昔より早く、逆に閉経は遅くなり、出産の機会も少なくなりました。これらはエストロゲンにさらされる期間が長くなったことを意味します。こうした背景から、乳がんが発病しやすくなったと考えられています。
乳腺症にかかったことのある人は、乳がんの発生頻度が高いという統計もありますが、これは特殊な乳腺症に限ってのこと。ほとんどの乳腺症は、乳がんのリスクに影響しません。
検査では、まず触診をして、しこりの大きさやかたさ、位置などを調べます。その後、超音波検査や乳房を挟んで撮影するX線検査(マンモグラフィ)を行います。これらの画像をみて、しこりや石灰化像の特徴から診断します。それぞれの検査時間は15分程度で、結果はすぐにわかります。さらに検査が必要な場合には、しこりの部分に細い注射針を刺して細胞を取りだし、顕微鏡で検査をします。あるいは局所麻酔を使ってしこりの一部や全部をとって調べる場合もあります。
乳腺症の治療は、強い痛みに対する内科的治療が主体です。痛みが軽度のときには特別な治療は必要ありませんが、痛みが非常に強く、日常生活に支障が生じる場合にはホルモン剤などの薬を用います。
食事療法としては、カフェイン摂取制限、脂肪制限、ヨード摂取などが有効といわれています。女性ホルモン剤の服用は避けたほうがよいでしょう。
乳腺症以外で乳がんとまぎらわしい乳房のしこりには、乳腺線維腺腫、葉状腫瘍があります。乳腺線維腺腫は20~30代の女性によくみられる、良性の腫瘍。治療はとくに必要ありませんが、大きなものは手術で摘出することもあります。葉状腫瘍は40歳代に多く、発育が急速で10センチメートル以上になることも珍しくありません。悪性の頻度も20%程度みられるので注意が必要です。






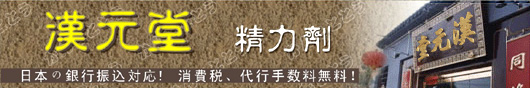
 勃起促進(EDの治療)
勃起促進(EDの治療)