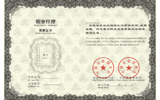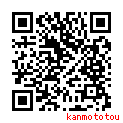肥満が画像診断の妨げに
X線や超音波などの画像技術に医学が大きく依存するようになってきているが、肥満が原因で画像検査による決定的な診断ができない事例がこの15年で2倍に増加していることが明らかになった。肥満はさまざまな疾患のリスクを増大させるばかりでなく、検査も制限してしまうことに気付いていない患者が多いという。
米マサチューセッツ総合病院(ボストン)のRaul N. Uppot博士らの研究グループは、1989~2003年に同病院で実施された放射線診断の記録を見直した。その結果、患者の体格が原因で画像の質が悪く、読影が困難だった症例が1989年には0.10%であったのに対して、2003年には約2倍の0.19%であった。
画像のタイプによっても差がみられ、肥満による影響が最も大きかったのは腹部超音波(1.9%)で、次いで胸部X線(0.18%)、腹部CT、腹部X線、胸部CTおよびMRIが続いた。この結果は、医学誌「Radiology」8月号に掲載された。
脂肪が厚いと超音波やX線が通りにくいという問題のほか、CTやMRIには、台の耐重量や開口部の広さという別の問題もある。メーカー側でも対策を取り始めており、装置の耐重量はCTで450ポンド(約200kg)から550ポンド(約250kg)に、MRIで350ポンド(約160kg)から550ポンド(約250kg)になったという。しかし、たとえ患者が装置に納まっても、より多い放射線量を用いるという、さらに重要な問題につながる。
問題は診断だけにとどまらない。米マイアミ大学ミラー医学部放射線医学教授のJourge Guerra博士は、体重が400~600ポンド(約180~270kg)といった患者を受け入れることで、X線技師がけがをしやすくなる、特別な設備やベッドが必要となる、画質が悪いので検査や治療に時間を要し、ほかの患者の受け入れにも影響が生じる、などの問題を挙げている。同大学では、新しい病院の建設にあたり、患者の3分の1が350ポンド(約160kg)より重いと想定しているという。






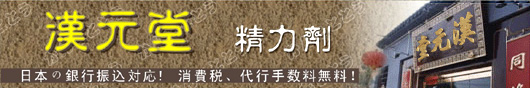
 勃起促進(EDの治療)
勃起促進(EDの治療)