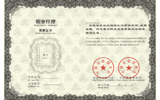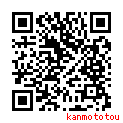肥満により消化管内の細菌構成が変化
肥満は健康を害するだけでなく、消化管内の健康的な細菌構成も乱すことが新しい研究により示唆された。この知見の意義については明確ではないが、新しい肥満治療の可能性につながるものであり、肥満に関する未踏の研究分野を切り開くものだと専門家は述べている。研究は、英科学誌「Nature」12月21日号に掲載された。
一般に細菌は悪いものと考えられているが、実際には体内の一部の細菌は善玉であり、消化系では食物の分解をはじめ、いくつかの役割を担っている。米ワシントン大学(セントルイス)医学部の研究グループは、腸内細菌の構成が痩せた人と肥満の人とでは異なるのかどうかに着目し、肥満者12人の糞(ふん)便中の細菌を1年にわたり研究。この間、被験者は徹底したダイエットを実施した。
その結果、肥満者は痩せた人に比べ、バクテロイデテス(Bacteroidetes)類の細菌が少なく、ファーミキューテス(Firmicutes)類が多いことがわかった。また、同じグループによる関連研究では、これと同じような細菌構成をもつマウスは、食物からカロリーを効率よく取り出すことができ、これが体重増加を招くことも明らかにされた。しかし、肥満者がダイエットを続けることによって、細菌構成は痩せている人に近いものになっていったという。
研究を率いた同大学ゲノム科学センターJeffrey Gordon博士は、この2研究によりいくつもの疑問が提起されると述べている。一部の成人が肥満になりやすいのは、もともと腸内のバクテロイデテス類細菌が少なくファーミキューテス類が多いためのか。また、バクテロイデテス類が少なくファーミキューテス類が多いという特徴が、肥満状態の定義づけあるいは肥満のリスク増大の指標となるのか。腸内細菌を安全かつ有益な方法で意図的に操作して、エネルギーバランスを制御することは可能なのかといった疑問が挙がっている。
腸内細菌が肥満体質の原因となるのか、腸内細菌の変化が実際に体重に影響を及ぼすのかを判断するには、さらに研究を重ねる必要があると専門家は指摘している。現在のデータでは、腸内細菌と体重との関連は示されているものの、腸内細菌が体重の調節に寄与しているかどうかは明らかにされていないという。






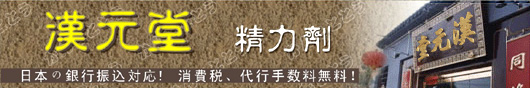
 勃起促進(EDの治療)
勃起促進(EDの治療)