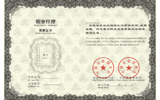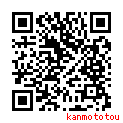低脂肪食は閉経後の癌(がん)や心血管疾患リスクを減少せず
米国政府による女性の健康イニシアチブ(WHI)研究で、脂肪分を抑え野菜や穀物、果物を多量に摂取する低脂肪食が、閉経後の女性の乳癌(がん)、大腸癌、心血管疾患のリスクを軽減しないという3件の報告が、米国医師会誌「JAMA」2月8日号に掲載された。WHIは、閉経後女性の死亡、障害、生活の質(QOL低下の原因を特定することを目的とした、現在進行中の15年間にわたる大規模研究。
同研究では、閉経後女性約5万人が、脂肪を減らし(全カロリーの20%)、野菜や果物(1日5食servings分以上)と穀物(1日6食分以上)を多く摂る食事に変更する群と、変更しない対照群にランダム(無作為)に割り付けられ、8年間追跡調査された。
低脂肪群では、対照群より乳癌リスクが9%減少したが、統計的有意差はなかった。しかし、開始時に高脂肪食を摂取していた人ではリスクが有意に軽減し、効果がある可能性を示している。大腸癌リスクも低脂肪群で減少しなかったが、癌の前駆体であるポリープの発生は減少しており、効果が後に発揮される可能性はあるという。
冠動脈性心疾患、脳卒中などの心血管疾患のリスクも有意に減少せず、中性脂肪値の低下などの危険因子(リスクファクター)軽減にわずかに効果がある程度だった。しかし、米国立心肺血液研究所(NHLBI)のWHIプロジェクト委員Jacques E. Rossouw博士は「総脂肪量を減らしても心疾患への効果はなかったが、飽和脂肪やトランス脂肪を減らした女性では有意に減少した。総脂肪量でなく特定の種類の脂肪に焦点を当てるべき」と述べている。研究者らは、高炭水化物摂取が体重増加をもたらさなかった点も記している。
心臓病専門医はこの結果の解釈に慎重で、米レノックスヒル病院(ニューヨーク)女性心臓治療主任で米国心臓協会(AHA)のスポークスウーマンNieca Goldberg博士は、「最も困るのは、今回の結果を理由に高脂肪、高カロリーの食事を摂るようになること。心血管疾患リスクの軽減は、いくつかの組み合わせでできることで、食事、運動、薬剤のどれか単独ではできない」という。また、閉経後でなく若いうちに低脂肪食を始めると大きな効果があるという意見もある。
Rossouw博士は、癌予防の効果は時間とともに出てくる可能性があると述べている。今回の被験者の90%は今後5年間追跡調査され、現在のデータも精査される。具体的な食事成分が効果を示す可能性も残されているとのこと。






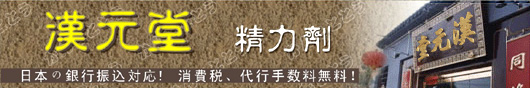
 勃起促進(EDの治療)
勃起促進(EDの治療)